日光市には、足尾銅山跡があります。古河財閥の礎になった鉱山で、日本一の銅の産出量を誇りました。最盛期の人口は県都宇都宮に次ぐ、10万人暮らしていたそうです。日本の公害の原点として、また田中正造がその住民救済に命をかけたことで、日本史にも刻まれております。
が約50年前に閉山。現在旧足尾町の人口は2000人を下回っております。
石見銀山のように世界遺産登録を目指すという運動もありますが・・・・・・残存遺構は結構傷んでおり、その実現は・・・・・・????です。


そんな銅山の旧施設の一部が「産業遺産」か、それに類する価値があるらしく。その保存、そして建家の再建が計画されたようです。当社は下請けですが、その基礎の補修作業。そして内部の古式漆喰壁の再生がオーダーされております。
その作業開始が24日から予定されており、都合4日間の工程でした・・・・・。
が。信じられないようなアクシデントというか、見込み違いで、仕事がぶっ飛んでしまいました。
100年ほど前の建築ですから、石積みとコンクリートの併用の基礎部分に土台の木材を回す、という基礎でした。
その石やコンクリート部分の不陸を調整し、新たに設置する土台の木材が水平に配置できるように・・・つまり下地調整・レベル調整が最初の仕事だったんです。
それで石やコンクリを削ったり、盛ったりする道具と材料を持っていったんです。
ところが・・・・・・。
そうした調整って、せいぜい+-10-40mm 内外という前提なんですが・・・・・・墨というかレベルを測ってみると・・・・・・
なんと既存基礎の、最高部と最下部では240mmもの高低差があることが発覚!!!!!!!。

分かりやすくいうと、家の基礎があっちとこっちで24cmも高さが違う!!!!!ということなんです。こんな基礎の上に建家建たないですよね。傾いてしまいますよね。
幾ら100年前の建築でも、当時建設の粋をかけた鉱山の施設です。その後の地震等で、傾いたと思うのが自然でしょう。しかし基礎とその上に乗っている機械設備が、産業遺構なのに、その基礎が壊れているのでは、工事の前提というか設計のリセットが必要なわけで・・・・・・。
当社の仕事は4日どころか、初日で一旦中断です。
まあ工事始まる前に、というか設計の段階で測量してあるのが普通だと思うけど・・・・・・・・・。
ま波風立ちますから、これ以上言うまい。
「補修」というレベルの作業でなく、おそらく、基礎を打ち足す、という作業になるでしょうから・・・・・当社の仕事ではなく、きっと一日で終わりですね。
ま、こんなこともたまには起こりますわ。
ランキングポイントアップのため記事が参考になったなら、テラ銭代わりに下のバナーをクリックしてくださいませ。毎度のご協力お願いします。
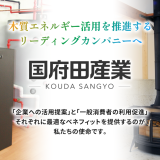















コメント